ラック車の需要が増大した60年代
1960年代の高度成長でコカ・コーラは爆発的に普及し、ライバルのペプシや、国内飲料メーカーのルートセールス市場参入で、ラック車の需要も増大していく。
須河では、重くて腐食しやすいスチール製ボディのアルミ化に1962年に着手。1964年にはもうアルミ製が主力になっていたという。
それとは別に、配送する清涼飲料水も多様化を始める。同じ1964年に従来なかったホームサイズ500ml瓶が登場する。その一方、1957年の缶ジュース誕生以来、1965年に缶コーラ、1969年に缶コーヒーが登場して、清涼飲料水の容器も少しずつ変化していった。
積荷の変化は当然、ラック車の姿を変えることになり、レギュラー瓶とホームサイズ瓶が混載可能なラックや、紙箱の缶ケースではラックと異なる荷室が求められた。1973年、これに対応してラック車に缶ケース専用室を併設した「ラック&ベイ車」が開発された。
そして1975年、日本で缶飲料と自動販売機が実用化されて急速に普及。容器の主流は本格的に缶へと移っていく。
ボトルカーが使いやすく進化し始めた70〜80年代
1970年代は、ボトルカーの使いやすさも向上していく。
須河の資料では、大量の重い液体の積込作業を省力化するためパレット積載化を図ったタイプ(1976年)、ドロップフレームにより荷台を低床化したタイプ(1977年)、カゴ台車積載に対応したタイプ(1979年)を相次いで開発してきたことがうかがえる。
ドロップフレームシャシーは、複数のトラックメーカーが4トン積中型トラックや3.5トン積小型トラックに設定したこともあって、80年代は「低床ラック&ベイ車」が全体的に普及していった。
なお、1980年前後には、ボトルカーメーカーとして北村製作所、札幌ボデー、加藤車体工業(現パブコ)、埼玉自動車工業、フジ自動車ボデー製作所、東神自動車工業所といった企業も名を連ねるよになった。同時期に富士見製作所の名が消えてもいる。
現在のボトルカーのスタイルが確立した90年代
1980年代を過ぎると、荷台に引き違い式ドアを備えたボトルカーが見られるようになる。また、1982年にはルーフに容器回収ボックス、いわゆる廃カップの前身が登場する。
そして80年代後半にかけて、ラックを艤装しない缶ケース専用ボトルカーが現れはじめ、90年代になると外観的には現在のボトルカーとほぼ同じスタイルになった。以降は、設計最適化による重量軽減などが進められてきた。
1990〜2000年代にかけては、ボトルカーメーカーとして東洋ボデー、SGモータース、不二自動車工業といった社名が見られるようになる。また自動車メーカーでも、メーカー完成車としてボトルカーを設定していた。
ただ、現在は撤退あるいは廃業しているボトルカーメーカーも少なからずあり、メーカー完成車としての設定は2010年代から見られなくなった。
ちなみに清涼飲料水の容器は、1996年に1L未満の小型PETボトルが普及し始め、2001年には清涼飲料水容器の半数を突破。現在では主流となっている。
サイズは異なるが、缶ケースもPETケースも紙製ボックスという荷姿のため、ボトルカーの荷室やスタイリングを変える必要がないものと考えられる。
【画像ギャラリー】ベース車がなつかしいな〜 須河車体の歴代ボトルカーを振り返る!(13枚)画像ギャラリー



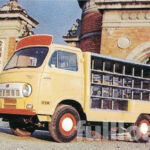






























コメント
コメントの使い方