物流の未来を見据えたインフラ戦略に
トラック運送業界は「2024年問題」に代表されるように労働力不足が深刻になっている。自動物流道路は物流の未来を見据えたインフラ戦略として、2030年に9億トン相当と推定される輸送力不足や、カーボンニュートラル実現に向けたCO2排出量の削減に対応する、新たな物流システムとして提案されたもの。
自動物流道路はトラックドライバーの労働時間にして約2万人日~5.7万人日(不足する輸送量の8~22%)をカバーし、CO2排出量は年間で240万~640万トン削減すると想定されている。
今年、公的機関と民間事業者の情報共有のためのコンソーシアムが設置され、最終とりまとめ時点で104社の民間事業者が参加している。
今後は、今年度の実証実験で明らかになった課題の検証、他の輸送モードとの連携、先行ルートの運用開始などを予定している。また、JISやISOなど規格化を通じて国際標準とすることを検討し、「荷物が自動で輸送される世界」の実現において日本が世界をリードすることを目指すという。
物流の自動化は世界各地で進められているが、技術開発の先行する地域が多い印象で、規制当局と事業者が一体となって制度と技術の両面からアプローチしているのが日本の自動物流道路の特徴だ。
なお、事業費や収入などの見積もりも示されている。本体部分の事業費(工費)は地上設置の場合10km当たり約250億円、地下設置(深さ40mの小口径トンネル)の場合、最大で同800億円となる見込みだ。コンソーシアムは東京・大阪間(約500km)で供用開始された場合の年間収入を3000億円と試算している。
全く新しい物流インフラの構築には多額の費用と長い時間がかかるが、商用輸送専用の道路となるため事業収入の見通しは立てやすく、実現にむけて動き始めた自動物流道路は、日本の新たな大動脈となる可能性を秘めている。
【画像ギャラリー】動き出した「自動物流道路」のコンセプトと海外事例(7枚)画像ギャラリー
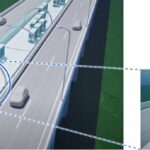
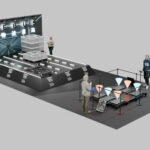
























コメント
コメントの使い方