トラックドライバーの誇り その43
規制緩和が行なわれた結果、雨後の竹の子のようにいろんな人間が運送業界に参入してきました。元ドライバーあり、水屋の配車係だった者、それなりの欲を持っていた者、また、細々と軽貨物などでやっていた者等、さまざまな人がいます。
特に現在深刻な状況に陥っているのが元ドライバーで、勧められてトラックを持つようになった者でしょう。その人たちは営業能力がなく、自分が仕事を貰う会社からしか仕事がありません。当然、その人たちは言いなりの運賃でしか運べないのです。
さて、規制緩和以来、運送業界だけが世間の流れと逆行して、無駄な水屋の数が増えて、実際に走る運送会社に渡る金額が縮小されたのか……。
当然それは、それまでトラックを持って走っていた会社がトラックを減らし、仕事を下請けの取引先に回すことが増えたからです。それが、規制緩和以来、中小の業者までがそんなことをするようになったのです。もちろん、荷主の無謀な運賃引き下げもあります。ダンピング業者が持ってきた金額を鵜呑みにして、それを今まで取引をしていた会社にそのまま押し付ける。そんな話は日常茶飯事にあったようです。
もちろん、荷主である生産業者も経営環境は苦しかったのでしょう。また、それまでの事情通のベテラン担当者から、若手の何も知らない人物を配して、無謀ぶりを黙認していたということもあります。
しかしながら最も深刻な問題は、中間に入る水屋の多さではないでしょうか。それが増えこそすれ減っていない。特に長距離の帰り荷物の場合に際立っています。
その中には、元水屋の配車係が独立して、新規の水屋になった例が数多くあります。彼等が持ってきた仕事は、とにかく安かった。でも、走る業者がいたからこそ、彼らの仕事が成り立っていたんですね。
また、多くのトラックを保有していた会社が、人件費やトラックの維持費を節約するために、電話一本で数千円単位のピンハネが出来る道を選んだ。ある意味、当然の成り行きなのかもしれません。なぜなら、バブル崩壊時に大手の会社がやったことを、規制緩和で中小業者や地場の大手までがそれに習ったのです。
そして、それがいびつな運送業界の実態を加速させてしまったのです。
現在、中程度の荷主を抱えている運送会社や小程度の運送業者も、閑散期に遊ばせない程度のトラックの台数に減らしています。残りを他の小零細業者に頼むわけです。
必然、実際に走る運送会社は、最低の運賃で仕事がない時期もあり、苦労の連続です。
これが規制緩和以降、ピンハネが多くなった実態です。つまり、トラックを保有している会社ほど、仕事を持っていないということです。
トラさんのブログ「長距離運転手の叫びと嘆き」
http://www.geocities.jp/boketora_1119/







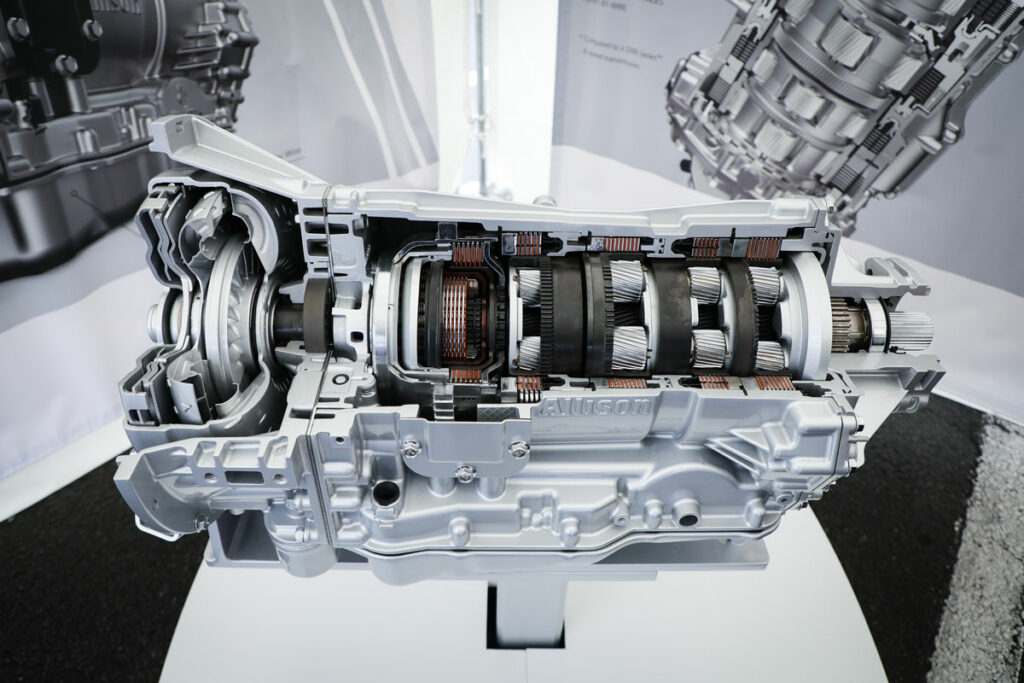











コメント
コメントの使い方