トラックドライバーの誇り その42
バブル崩壊時に運送業界に何が起こったか?。一番顕著な例を挙げれば、家電メーカーが保有していた運送会社の例があります。
家電メーカーの全てが、○○物流と称する運送会社を子会社として持っていました。しかし、バブル崩壊以降、運賃を抑えられた?せいなのでしょう、人件費やトラックの維持費が占める割合が大きくなり、経営を圧迫していったのです。それを無くすために彼らの全ての会社が、トラックを手放し、運送を外注するようになりました。
そして、自らはメーカーからの運送依頼を受けては取引のある運送会社に流すようになったのです。
もちろん、これは大手家電メーカー系の運送会社だけの話ではありません。
大手の運送会社では倉庫業に専念し、トラックは別会社の子会社を作り、ピンハネをしている会社はたくさんあります。当然、ドライバーの雇用条件は厳しくなっています。また、取引先もワンクッション(子会社が)入るために、その分運賃も低く抑えられました。
その結果、何が起きたのか? 私は以前、バブル崩壊以降も住宅関連産業の仕事があったので潤っていたと書きました。住宅金融公庫が特別融資をしていたのが大きな要因です。でも、それだけではありません。
一部の大手運送会社が自ら保有するトラックを手放すことで、他の中小零細業者に回る仕事が増えたのも、運送業界の落ち込みが少なくて済んだ大きな要因のひとつだと考えています。ただし、これは数字的な根拠や資料の裏付けはありません。あくまでも私の仕事をした実感と経験による推測です。
この時点で、荷主が支払う運賃はかなり抑えられていたと思います。それは、私自身も実感として持っていました。だけど、仕事には不自由しませんでした。それが、一変したのが規制緩和です。
規制緩和までは、運送業界に参入するにはそれなりの高いハードルがありました。つまり、バブル時にトラックの台数は膨らみ切っていたとはいえ、それでも業界に分け与えられるパイは、(小さくなったとはいえ)あったのです。
そして、規制緩和以降、何が業界に起きたのか……。
つまり、
*運送業界では、規制緩和以来、それが逆行しているのです*
次回に譲りたいと思います。
トラさんのブログ「長距離運転手の叫びと嘆き」
http://www.geocities.jp/boketora_1119/







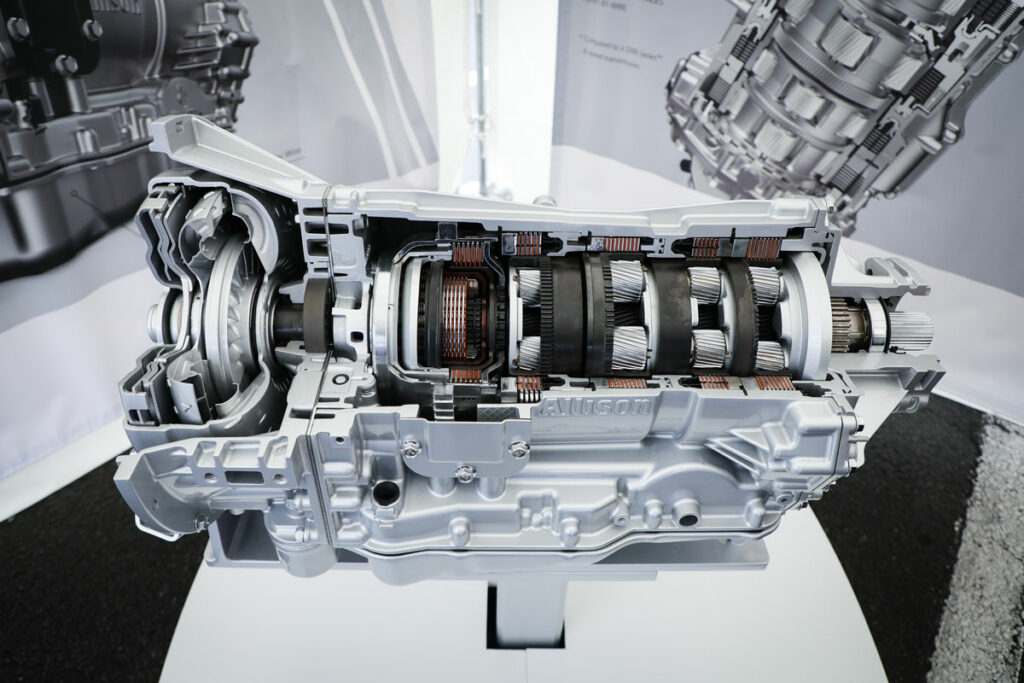











コメント
コメントの使い方